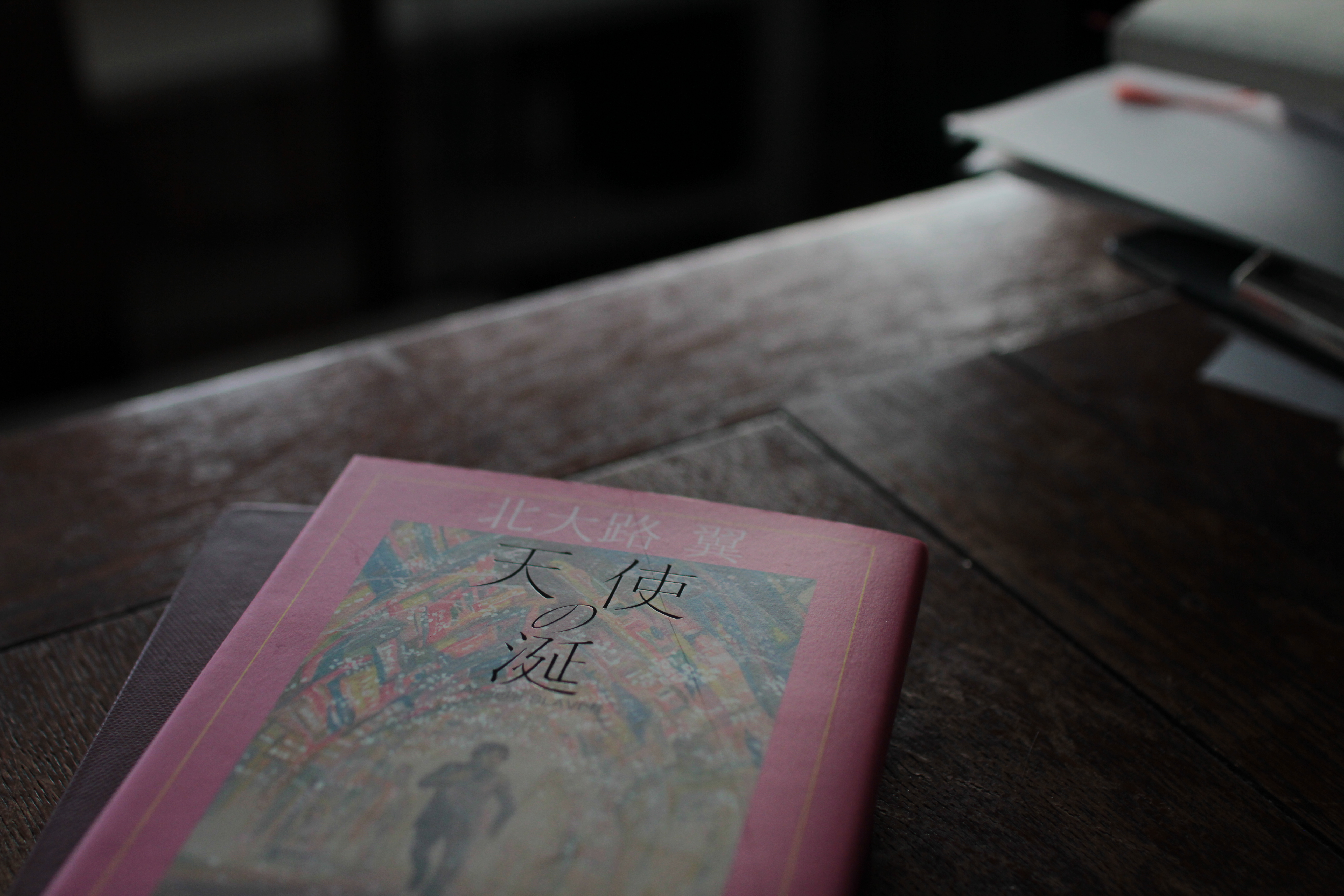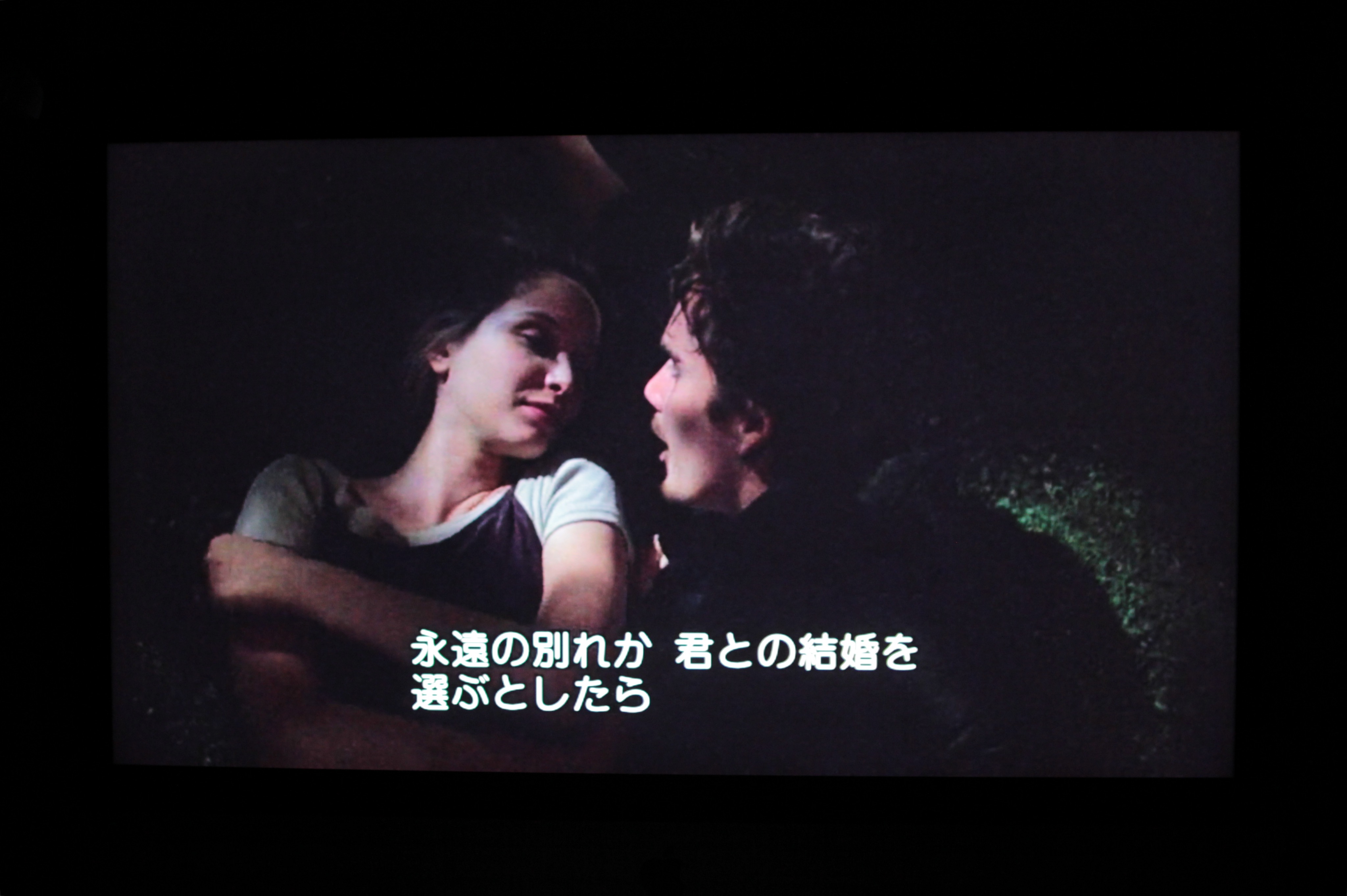先日、夫の姉Aさんから「午後暇ならお茶でもしよ〜」とラインが来て、昼ごろAさんがウチにやってきた。キムチチヂミ1を焼いて食べてから、どこいく〜とかいいながら猫と遊んでダラダラしていたらもう15時だ。ココ最近はこんな時代なので地元の駅のショッピングモールや百貨店2を冷やかして過ごしていた。けど「化粧品がみたいような気がするような」というAさんの意見3で「フタコ4でもいくか〜大っきらいだけど」ということになりクルマを246へ走らせた。多摩川の手前の側道に入る分岐路のところで、なぜか「渋谷にも行けるけど」と私はひとり呟き、Aさんの意見5を聞きもせず、左に出したウインカーを止めて246を直進した。ドライブしたい気持ちがあった。
車中で会社での出来事などをぺちゃくちゃ喋っていたAさんの「化粧品がみたいような気がするような」気持ちは渋谷に着く頃にはすっかり無くなっており、それに代わり「クレープが食べたいような気がする、いや絶対食べる」という舌になっていた。クレープよりホルモンが好きなAさんにしては珍しい。クルマを西武のP6にぶち込み、センター街でクレープを食べ7、ぶらぶらしていると、公園通りの付け根の元マルイ(現MODI)で落合陽一の個展をやってることを思い出し、行くことした。Aさんは「大人かわいい女子」なので落合陽一とかに疎い人だが、かのじょが良く食事をするエグゼクティブのおじさまが落合陽一の開成の先輩で、最近その方の話の中に落合陽一が出てきたとかで、彼女にとっても落合陽一はタイムリーだったのだ。
落合陽一の個展は、いろんなごたごた抜きに、本当に素晴らしいものだった。皆さん知っての通り、答えのないような漠然とした現象(エクスタシイ問題8)に、問いや感情をぶつけ続けている私で、世の中のほとんどのことに首をかしげたり憤ったりしている私だが、色々なところで見聞きする落合さんの言葉は、いつなんどきでもやさしく私の腑に落ちてきた。
* * *
(ごたごた始まります)
かれは時代きってのサイエンティストだと思うけど、そしてアーティストだけど、何よりも詩人だと思う。詩は、芸術のはじまりとなった場所9だから落合さんが詩人であっても不思議はないんだ。かれの切り取る言葉とシーンは見事に調和し、私の思考をアートさせる。いや、調和ではないな、言葉による補足が作品に形を与えているように、最初私はそんなふうに作品を鑑賞していた。落合さんは、恐らくはそうなることを避けるため、あえてキャプションを「とってもとっても読みづらく」配置している。
しかし残念ながら?この人は言葉による表現が大層巧い。語る内容の抽象度が高ければ高いほど、文章の巧さは引き立つ。詩人に近づく。
落合さんにとって写真を撮ることは、このような行為だ。
以下は展覧会で掲示されていた文章の中の一部の抜粋です。読むと深く理解できます。難しい話ではないです。
”スナップショットが好きだ.今この瞬間を捉えてそれを過去にしてゆく作業の中で,切り取った一瞬をコンテクスト10で結んでいく.時間と空間で結実したひとつなぎの現実をキャンバスにして,その瞬間と瞬間の光のよせ集めで何かを描き出そうとする作業は,手触りのある現実と思考を行き来しながらも現実という共有物を使いながらコンテクストを紡ぐ作業だ.なぜ今この写真がこの場所で選ばれているんだろう.これは誰の手なんだろう.何につかう装置なんだろう.これは何をしているんだろう.この形や光が意図するものは何なんだろう.絡みついた問いかけを繰り返して,情念と現実が反芻して練り上げられたコンテクストを,あえてイメージのみを現前させながら描き出してゆく.批評性や社会性のあるものだけを芸術と呼ぶ安寧な領域のことを忘れ,絵を書くようでいて物語を紡ぎ,物語を紡ぐようでいて,あくまで現実の世界や社会の中から見つけてきたものだけを現前させる.あるがままの現実を具材に,言外のコンテクストを追いかけるスナップ写真の形を愛している.”
そのようにして切り取られた、鯨の歯(”現前の具材”)の写真にはこのようなキャプション(”物語”/”言外のコンテクスト”への道標)がある。
”歯鯨の環世界を覗いてみたい.音と光の波の合間に生きる日々の中で,鯨の身体性に思いを馳せる.”11
瞬間、私は以前どこかで書いた、ダイアン・キートンが語ったアル・パチーノのプレーンさ12について思い出していた。そこで私は「時の中に光が溶け込み、柔らかく曲がり、更には可逆となり、何もかもを可能にしている時代で、不可能でありたい、と出し抜けに思った。」と書いた。歯鯨はアル・パチーノに他ならなかった。
* * *
ここまで、かれの紡ぐ物語(言葉)の方に奪われて、物語を鍵にして作品に入っていた私の時間が、一瞬張り付いた瞬間があった。蝶を写した一枚のプラティナプリントの、4メートルほど手前の地点だった。
俄に皮膚が泡立ち、その後2秒くらいで急に視野が狭まり、同時に聴覚がシャットアウトする。その間は呼吸もしていないらしく、気づくと苦しさを伴っている。
MODIは元マルイだった館で、この展覧会は、その2階をぶち抜きにしていた。
躯体が露出し、建物の裏側から、どこにも繋がっていないコードの先端が枯れた植物のように生えている。建設同時の手書きの指示のバランス、色ともに、この壁面はこのぶち抜きの廃墟の中でも、一等美しく廃れ、「もっとも価値のある面」と判断されたに違いない、と直感したら、次の瞬間そこに一羽の蝶が浮かんでいるのがみえた。
感情が身体を制し、もう泣きそうだった。
廃れた場所に蝶が飛んでいるのってなんて美しいんだろう13。
この廃墟は、また近いうちに新しい廃墟になって
この建物が立っている土地自体なくなるかもしれない
けど、この写真は500年後もそのままの姿でいるだろう14
2520年の世界では、この蝶はもっと美しいんだろう
ああ、ああ。15
しかも不思議だったのは、近寄ってから読んだキャプションだった。
タイトル/ 青
キャプション/ “青を感じるための物質的な追憶”
その瞬間、「この蝶は青だと思っていた」という自分の感覚が思い出された。
それは作品を見ているときから思っていたこととは違う、瞬発的な思い出し方があった。
さらに不思議なことにAさんも同じことを後から私に言った。
落合さんは、どんな手品を使ったんだろう。
さらにさらに、不思議なことに、この文章の校正のために夫にこの話をしていたら、「デジャヴってこと?」と聞く。「そうそう、そんな感じ」とか言ってたら「この展覧会自体がデジャヴをテーマにしてるんだよね?」と摩訶不思議なことを言ってくる。
言葉を失っていたら、受付でもらった紙に「未知は追憶できないが、思い出せないデジャヴュ=既視感を探すと、未知への追憶になるのではないかと個人的には思っている」と書いてある…。
そんなの知らなかったよ(読んでないだけ)。
真面目にどんな手品つかったの。
* * *
作品の横にキャプションとして”言外のコンテクスト”への道標が示すことは、その作品に入ってゆく鍵を渡すことだ。
作品を見た人は鍵を受け取り、丁寧に鍵を鍵穴に入れ込み、回して、扉が開き、その作品の中へ入ってゆく。恐る恐る。そして作品の中になんとか自分でパス16を作り、出てくる、といった感じ。この感じは、皆さんおなじみではないだろうか?
けれど、私の体験の中で、道標がない場合の方がキョーレツな体験になりやすい。
俄に皮膚が泡立ち、その後2秒くらいで急に視野が狭まり、同時に聴覚がシャットアウトする。気づくと呼吸もしていないので気づくと苦しさを伴っている。しばらくすると、この感覚すべてが多幸感や充実感に変わり、そして悲しくなる。幸せな悲しみ。幸せで泣いているのか悲しくて泣いているのかわからなくなる。そして数時間後、なぜか元気になっている。
私はこの感じを以て、これをエクスタシイと呼んでいる。脱魂。
その時、その作品は本当の意味で自分の所有物になる。
けれども。
今ここ、コメダ珈琲店の2階の席に、パン職人たちの働く姿を描いたテラコッタの画がある。
不思議なことに、この数時間、この絵を私は100回以上見ている。
書きながら思考が絡まりつくと、この絵を見る、というルーティンが100回以上続いている。
その都度、このパン職人たちが、私をリセットしてくれる。
だから、皆さんにもこの絵を紹介したいと思った。
最後になるが、落合陽一の個展にはたくさんの花が届いていた。
その最左上位に、父親である落合信彦の花が配置されていた。