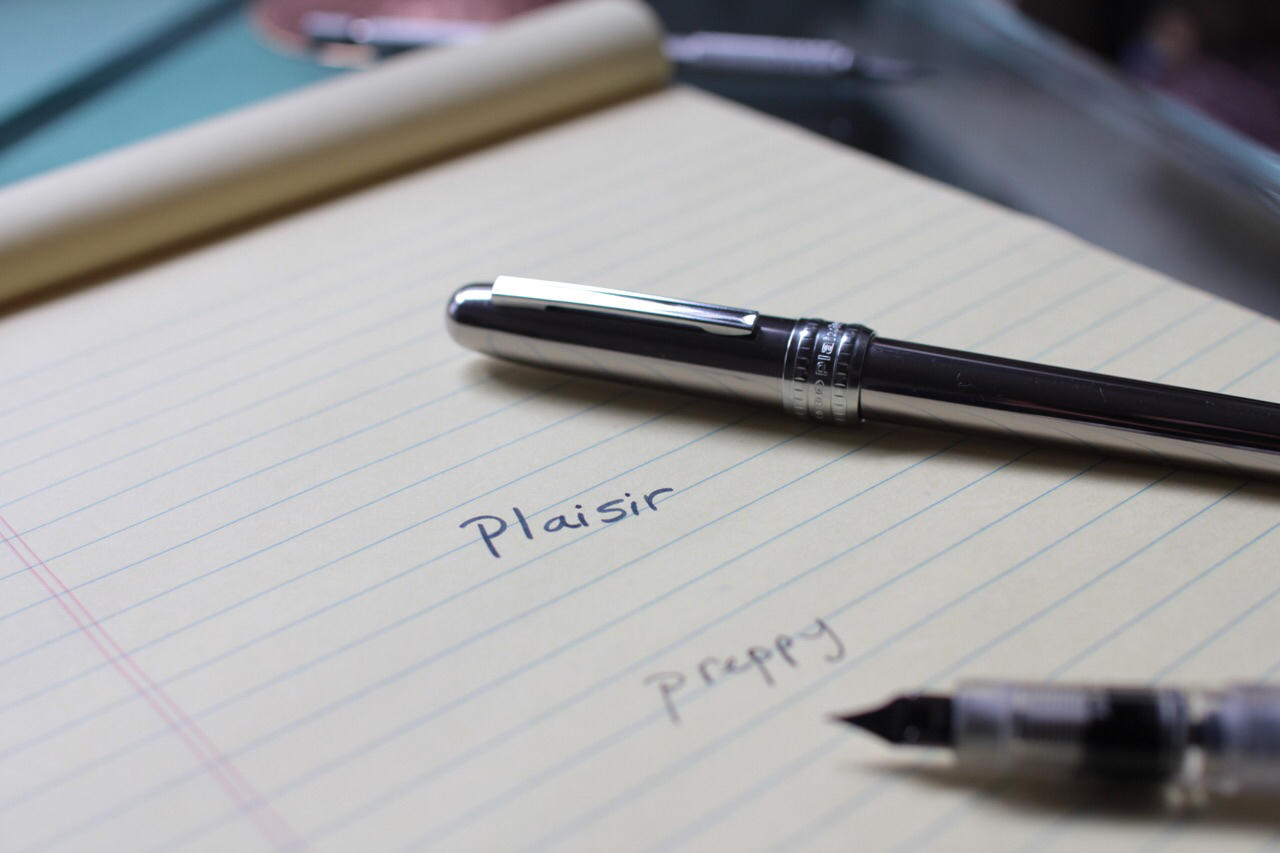横浜から引っ越すときに、友人たちがくれたカード。久しぶりに見つけて、読んだ。確か、引越しまでの数日飾っていた時に写真も撮っていたはずだった、と探した。ちょっとホームシックな金曜の夜。
今夜ふと戸川純の蛹化の女が聴きたくなって聴いてみている。ヤプーズとかも好きだった。よくよく思い出せば、私が高校一年生のころ、初めてインターネットで通販したのは、ゲルニカの何枚組かのCDだった。近所のレコード屋さんになくて、でも絶対欲しかった。
寒い新潟の冬でゲルニカやベルアンドセバスチャンの暗い曲をよく聴いていた。灰色をした空に掛かる、黄色と黒の遮断機を見上げた時に唇に触れた雪の冷たさ。そんな一瞬の風景がフラッシュバックする。その時着ていた、古着のラビットファーのコートや、そのポケットから出てきた1セントコインのことも、この声を聴いてるとどんどん思い出してきた。
98年ごろ通った原宿のパレフランスにあったHANJIROという古着屋さんは面白かった。広くて近未来的で宇宙的な(中学生の私にはそうみえた)明るい店内に、大量の古着が無個性の顔をして並んでいた。個性は選ぶ方に有り余っているから、そういう陳列がむしろありがたかった。まさに宝探しだった。
私の通った長岡高校は制服がなかった。そして私はルールに従順な方ではなかった。かといって、ファーのコート禁止と校則に書いてあるわけではなかった。学校中から恐れられていた担任の体育教官に「体調管理の観点で、防寒として着ています」と屁理屈を言った。私は一番前の席だったが別に怖くはなかった。
世界中から集めた美しいものリストがあれば、間違いなく選ばれるはずの、パッヘルベルのカノンの旋律に、勝手気儘な世界観が載っている。
正統なる純潔さ、ローマングラスの銀化した欠片、大変希少な蜂蜜。そういうものを想起させる。
もう今は2018年が来ようとしている。(2017.12.29)