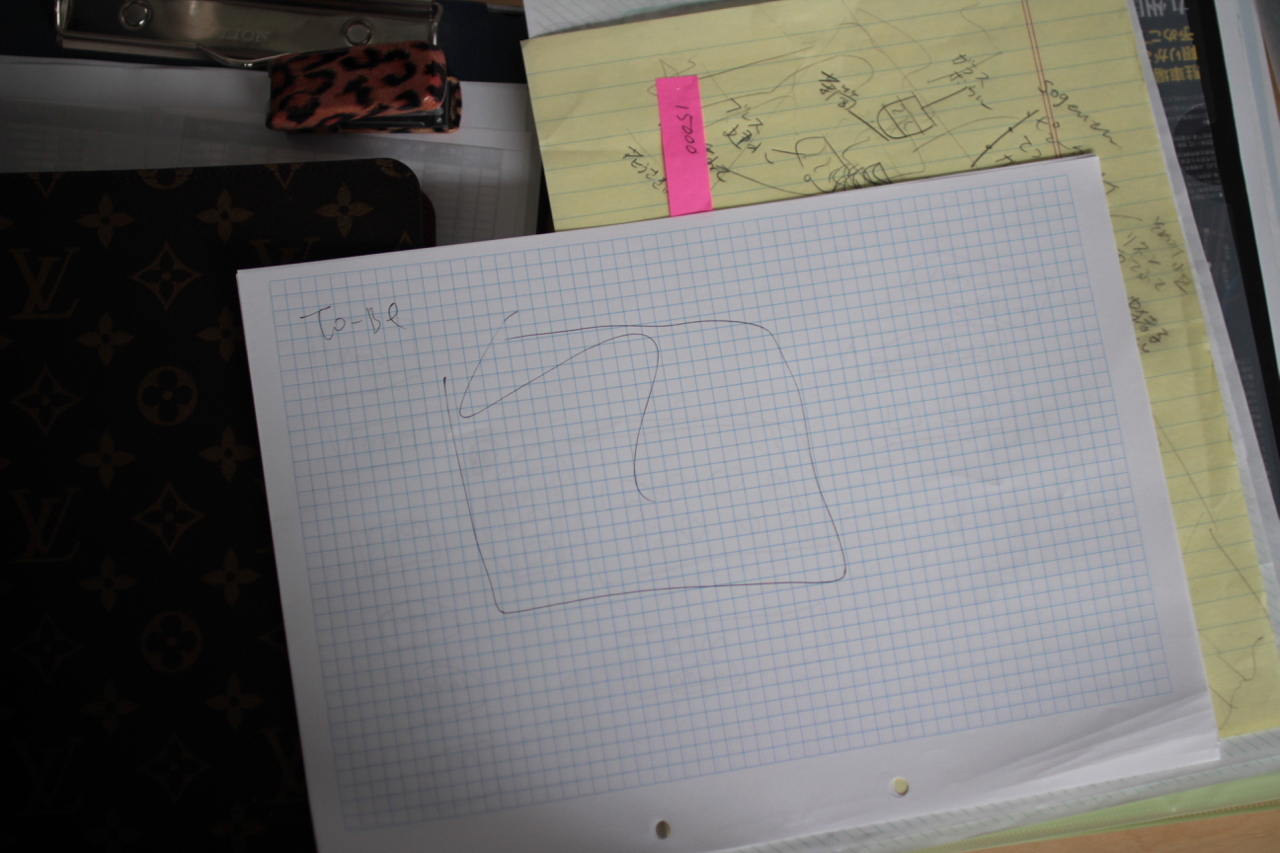溜め込んだアイロンがけをするために必要なものは、ジンと何度も何度も観た映画。オーシャンズシリーズにしてみる。何度も観てるからシーンとかストーリーも頭に入ってて画面を見ずとも鑑賞できる。スティーヴン・ソダーバーグってなんでセックスと嘘とビデオテープからデヴューしてこんな軟派な映画を撮ったんだろう。とか考えながら、ふとジェームス・スペイダーの金色の胸毛のこととか、そういうことをぼんやり考えられる余裕もあるし。ブラッド・ピットとジョージ・クルーニーの組合せは最高。ふたりの壮大な身内ネタを見せられているような若干の感触はありつつも。ベン・アフレックの弟のスペイン語もいい感じだし。そもそも先日姉が遊びに来てる時、コトの流れで藤井フミヤの動画を観ながらお酒を飲んでいたら、姉が観てる傍からどんどんフミヤにハマってゆき、私はどんどんアンディ・ガルシアにしか見えなくなってきた。その時から、近々アンディ・ガルシアの出演作が観たいと頭の片隅が思っていたのだった。アンタッチャブルかゴッドファーザーⅢかなーと考えてたけど、オーシャンズは手っ取り早くていいや。ジンはアイラ島のボタニストってやつ。日曜日の夜、ジンが切れた。近所の酒屋へ走った。味見でボタニストの小さいボトルと、保険でタンカレーを買った。ソーダで割ろうと思ってタンブラーに注いだのに、ソーダが切れていた。
「芸術と感情の記録」カテゴリーアーカイブ

白紙の未来
May 8th, 2018春の蛇
April 14th, 2018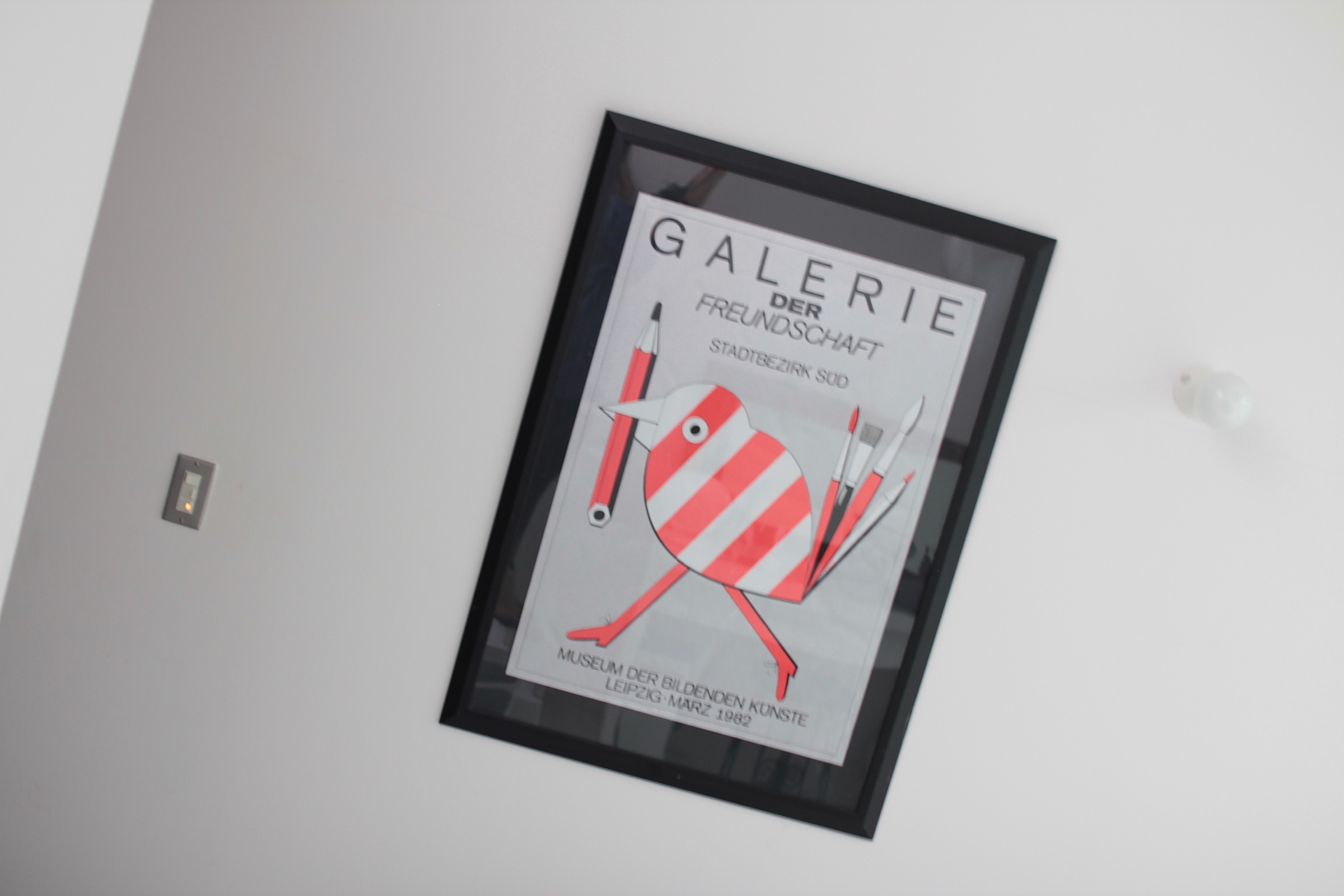
春です。
私が錆色の蛇のようにとぐろを巻きながら人をつかまえてはくだを巻いていた季節を過ぎたら空と海には桜が舞っていた。Kindleに齧りついて夢枕獏の空海や梁石日や開高健のアパッチ族を読み耽っていた。私の目は怪しく光り、頁を繰るときだけ人差し指を画面にかざして、決して何も肯定しようとはしなかった。木の芽どきにはその目は一層光り、鱗を逆立てて、それを擦り合わせ不気味な音を立てたかと思えば、尻尾をはげしく前後に動かして、ガラガラヘビのふりをした。小沢健二の新譜もいつからか聴かなくなっていた。木の芽はとっくに過ぎ、いくつかの花の季節も経た。蛇が結婚式で持ったマグノリアも終わって菫が咲いて、桜が散りはじめてやっと、この錆色の蛇はにょろにょろと、青いレンズのメガネをかけて視力矯正をして慎重に路地へ出てきたのだった。
蛇には仕事があった。阪急うめだのイベントだ。冬眠中の蛇は尾っぽを器用に操りMacで展示物をデザインしたり、カッターで封を切ったり、伊万里の古い器を並べた。設営が済むと、トム・フォードのヌードディップで囲んだ目の周りは真っ青になっていたが、完全に冬眠が明けていた。蛇はザラザラと音を立ててバイヤーのねえさん方たちと阪急うめだから新梅田食堂街へ移動し、尾っぽでレンゲを握って新喜楽の鴨鍋の汁を啜った。また胴に下げたルイヴィトンの鞄から尾っぽの先でやまつ辻田の粉山椒をつまみ出し器用にその封を切って「追い山椒」をしたのだった。蛇はナビオの駐車場までザラザラと音を立てて移動し、900円の駐車料金を払った。身体を滑り込ませるように運転席について尾っぽを巻きつけるようにギアをドライブに入れ、ハンドルを握って御堂筋を北へ爆走しだした。信号待ちで尾っぽを器用に操りiPhoneで岡村靖幸のsuper girlに合わせた。カーステレオから水色の澄んだイントロがこぼれだした。蛇は歌った。
春から夏にかけての蛇には注意だ。
小沢健二の新譜
February 17th, 2018
当時は暑苦しいものも嫌いだったし
子どもっぽいこともごめんだった
ボーイズとつくバンドは聴く気になれなかった
ザゼンも銀杏もテリヤキも
不潔そうで頭わるそうなバンドマンには興味がなかった
不潔そうで頭わるそうな男性は今だってごめんだけれど
小沢健二の新譜を聞いていた
素敵なオルガンは沖祐市なのかなと調べていたら
関連して峯田和伸と『ある光』をコラボしている動画があった
『ある光』自体が精製度が高くスピードが早く凍りついた水晶のように冷たい曲
雪がふる長岡駅の東口 高校の帰り道
終わりかけのルーズソックスを履いている女子は大抵ピンパーマの男の子と一緒に歩いていた
彼らの頭は驚くほど大きかったけど 大抵それらの男の子は可愛い顔をしていた
そういう子たちがGOING STEADYを聴いているという風俗は知っていた
冬の日 まだ中学生だった私
隣町に住む友だちに連れられて 知らない子たちが出るライブへ行った
私は原宿の古着屋で買ったファビットファーのショートコートを着ていたから寒い頃だったと思う
ステージの上で激唱している男の子はイケてなかったけど 歌っている曲は良かった
もしも君が泣くのなら僕も泣くと何度もシャウトする曲
コピーバンドだったことも全然知らなかった
金曜日の六本木
26時をまわった頃 オフィスに人は少なく 残った面子が誰ともなく誘い合った
レバ刺しが禁止された頃 六本木か赤坂付近で食事をしてからカラオケに入って朝まで歌った
毎週のことで誰が何を歌うかは大抵決まっていたし
カラオケではテキーラとレモンサワーしか頼まなかった
ある日誰かが聴きなれない曲を歌っていた 銀河鉄道の夜
すぐに上司と後輩の女子が歌う淋しい熱帯魚に掻き消えていった
東京スカパラダイスオーケストラと峯田和伸の『ちえのわ』
なんども自分の耳を素通りしていった峯田和伸の声を初めて自分の耳が捉えて胸をつかまれた
今だって認めたくない気がする
知恵の輪外して虚しくてまた元に戻した ばらばらにしたくない 離れたくないんだ
揃いの衣装も似合っている 股上の深い太くも細くもないセットアップ
春の玉川通り
神泉の近く玉川通りから 山手通りへ降りる松見坂の方へ
信号待ち 駒場のあたり 隣り合った黒いかっこいい車の黒いかっこいいサングラスの男性と目が合った
助手席の友だちが「あ、スカパラの人だよ。背が高くてすごくかっこいい人なの」
小沢健二の『ある光』を小沢健二と峯田和伸が歌うのをどきどきしながら聴いていた
数ある小沢健二の楽曲からこの曲を峯田和伸が歌うのは当然だなと感じた
この精製度が高くスピードが早く凍りついた水晶のように冷たい曲は峯田和伸にぴったりだ
敬虔さ
僕のアーバン・ブルースへの貢献
語り はかなり恥ずかしかったけど
もしも君が泣くならば僕も泣くと歌っていた人は峯田和伸だった
ちえのわを書いた人は松見坂で隣り合ったサングラスの人だった
峯田和伸がGOING STEADYだったことを知って いくつかの動画を観たけど
解散を惜しむ人々のコメントを読んでゆく内に うまく白けて
掴まれていた胸の皺は徐々に緩んでいった
今 小沢健二を交差するふたりの女の子
満島ひかりは触れるもの全てを腐らせる 容れ物の中の水が濁っているそれが彼女の魅力
当然ラブリーも腐った それまで小沢健二が歌ったラブリーしか聴いてこなかった私は 腐ったラブリーを初めて聴いた
二階堂ふみは氷と水の入った鉛を含んだグラスに沈め入れた水晶のような声をしている
小沢健二と岡崎京子が経験した長い夜に透明な石ころになって転がっているような
許し
私は彼の古い友を許せず「ファックス隠す 雑誌記事も捨てる」ふうだったけれど
汚くなることも弱いことも離婚することも 消費することも消費されることも 目が見えないことも許された今
私は彼の古い友を許せた気がした 疎遠になっている自分の友も
許しという魔法がかかった曲だった
幸福の浮遊感
January 6th, 2018
大山崎山荘美術館で開催されていた有元利夫展は、人生で幾度もない幸福な時間を私に与えてくれた。幸せや悲しみなどの感情は、できるだけ稚拙な表現で語りたい私である。
一枚目の作品は『室内楽』だった。人物が7つのあかい玉を弄んでいるというものだった。玉はおそらく音を意味しており、概念を表現したかたちだった。私の息は詰まった。夢中で絵を観た。じっと観ていると、ふと分かったことがあった。この絵の中の、どの線も、あと1ミリでも動かせないということに。完成されすぎているのだ。私の息の苦しさはそこにあったのかもしれない。
売店で関連書籍を全て購入し、喫茶で紅茶を飲みながら読んだ。読んでいるとぽろぽろ涙がこぼれてきて、かなり泣いた。私の涙は、この画家が夭折したこととおそらく関係していると思う。たった数年の間にどんどん生まれた作品。
泣いていてもしかたないので、もう一度、ゆっくり観てから帰ろうと離れの山手館へ入った。すると不思議な多幸感に襲われた。それはかなり簡素な多幸感だった。この広くもない空間に、十数枚の有元利夫の絵が掛けてあり、そこに自分がいること、ただそれだけのことをとても嬉しく思った。壁の色、絨毯の色、通路のアーチ、目に入る何もかもが完璧に私の心を捉えていた。冷たい水柱のようなものが腰の下から入って脳天を貫通し、リボンのような光とともに昇天しているような、ファンタジーの世界にいるような心地。セーラームーンが不思議な光の中で変身する時のような感じ。
泣きつかれた私は、帰り道、国道沿いのお店で、おうどんを啜った。お出汁の湯気は私をあたたかく包んだ。
そののち買い漁った関連書を読んだ。その中にこういう記述があった。
“僕の絵の中ではいろんなものが、たとえば紅白の玉や花、トランプや花びらなどがふわふわ飛んでいることがあります。花火も空に向かうし、はては人間そのものも宙に浮く。どうして飛んだり浮いたりしているのかと問われれば、僕にとってはそれがエクスタシーの表現だからとしか答えようがありません。《花降る森》を見て、あのひらひら散っている花びらは、とても地面に落ちるとは思えない、方向としては降るふりをしているけれど、あれは永遠にああいう風に漂って、決して落ちてはこないんだと思う、と言った人がいました。そう、エクスタシーと浮遊。音楽を聴いていても、その陶酔感は僕の中で浮遊に結びつく。だから、それを絵として表現したい時、それこそまさに通俗に徹し、臆面もなく文字通り人間や花を「天に昇」らせてしまうわけです。”
私はあの日、あの展示室で感じた多幸感を思い出し、ぞっとした。まさに私は浮遊していたといっていい。1ミリも動かせないように感じた玉や花びら。概念として存在する具象のあたたかそうでいて冷たい存在。
板垣足穂と共につくった一千一秒物語の銅版画集の文章を、一生懸命書き写してきたりして来たけれど、もはやどうでも良かった。記憶は身体の奥に残るこの多幸感だけで十分だった。